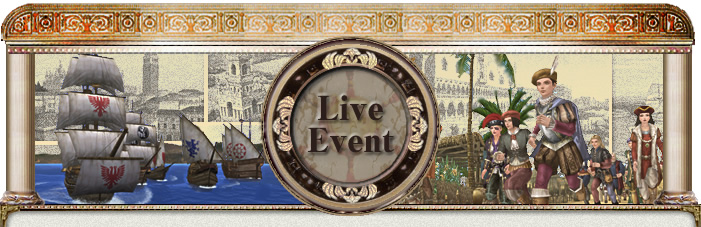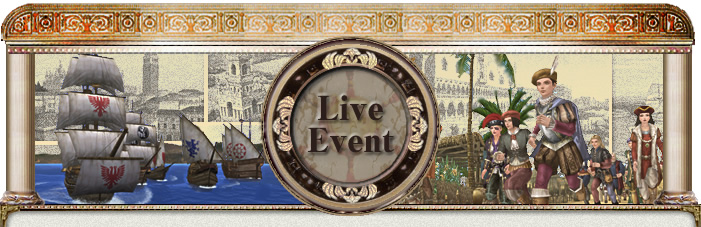僕は街に着くなり、微笑まずにはいられなかった。
街中がワインの香りに満ち溢れている。
月並みな表現だが、その芳醇な香り。
僕は行く先々で、貴族の晩餐会などに楽士として招かれることが
少なくない。有力者とつながりを持つことは、職業上悪くないこと
なので異存はないが、どうもあの「全てが作り物のような夢うつつの
空間」が苦手だ。生きている実感が湧かない。
嘘っぽい感覚に囚われる。
あの空間で僕を一番居心地悪く感じさせるもの。
それがいわゆる「高価なワイン」の香りだろう。
今のマルセイユにはそういったものは一切ない。
拙い演奏と拙いステップだけど、魂の躍動に身を任せて歌い踊る者。
飲みすぎて酔っ払い、騒ぐ者。
そして、人々の気持ちがこめられた、出来たてのワイン。
格調高く品があるものではなく、もっと親しみやすく、
生命力に満ち溢れている。
それが本来の祝い事にあるべき姿ではないだろうかと、僕は思う。
僕は少しの間街を歩いていた。祭りを楽しむ人たちに声をかけながら、
まだ、肝心のワインを堪能していないことにやっと気付いた。 |