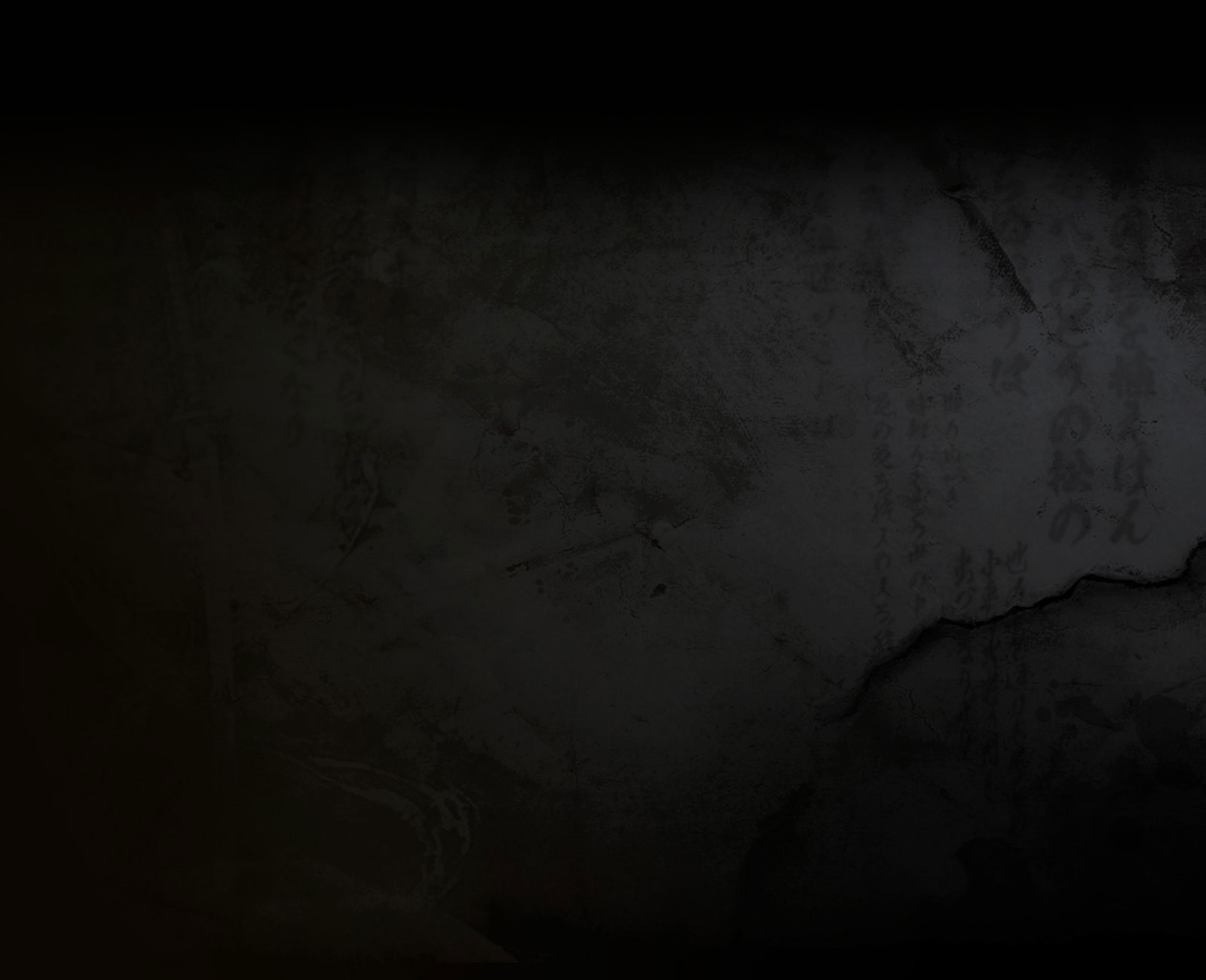
NEWS
雑賀衆を束ねる「雑賀孫一」や、新たな妖怪「鉄鼠」などゲーム情報を紹介2020/01/16
雑賀衆を束ねる「雑賀孫一」
雑賀孫一 声:加瀬康之
紀伊国(現在の和歌山県)を本拠とする雑賀衆の頭領。孫一とは雑賀衆の頭領が代々受け継いだ通り名で、本名は鈴木重秀(すずきしげひで)。前作で登場した重朝(しげとも)の先代にあたる。雑賀衆は依頼を受けて各地へ派兵する傭兵集団で、鉄砲や抱え大筒など砲術に長けた。戦は金次第で引き受け、特定の主君を持たない。依頼を受けて石山本願寺に籠もり、織田信長とは熾烈な攻防戦を繰り広げたという。

巨大なネズミの姿をした妖怪「鉄鼠(てっそ)」
鉄鼠(鉄鼠)
鉄鼠は怨念を抱いて死んだ僧侶が巨大なネズミの姿の妖怪と化したもの。ネズミは古来、最も身近な害獣であり、弥生時代の高床式倉庫にはすでにネズミ返しの工夫が見られる。ネズミの食害は穀物だけでなく和紙にも及んだため、多くの書物を蔵する寺院にとってネズミの害は深刻であった。仏門の敵というべきネズミの姿に僧自らがなるというのは、仏門に対する深い絶望と憎悪があったものと推察される。

牛鬼(ぎゅうき)
蜘蛛に似た脚を備え、牛に似た姿をした巨大な妖怪。性質は非常に獰猛かつ残忍で、毒を吐き、人を食い殺すことを好むという。水と関係が深い妖怪であり、海岸や川の淵、滝壺での目撃例が多い。西日本の各地に「牛島」「牛鬼淵」「牛鬼滝」などの地名が残されている。

新たな戦いの場
小谷城(おだにじょう)
浅井家の居城として急峻な小谷山に築かれた城。かつては尾根沿いに建つ小規模な城であったが、麒麟児と評された浅井長政によって先駆的な普請技術が採り入れられ、複雑な構造の城郭や曲輪(くるわ)が折り重なる巨大な山城となった。

石山本願寺
大坂に栄えた石山本願寺は、堅固な防壁で市街を囲んだ城郭都市である。海につながる運河を堀とし、防災と籠城時の利水を兼ねた巨大な溜池を備えている。多くの巨石を礎石として防塁としたため石山の名で呼ばれ、諸侯と対立した戦国期には、大名をも凌ぐ戦力を誇った。

守護霊

「九尾」の守護霊技。目の前に出現した九尾が5つの狐火を放つ。狐火は飛び跳ねるように動きながら扇状に広がり、広範囲の敵にダメージを与える。狐火は幻のような性質を持ち、壁を通り抜けることができる。














