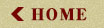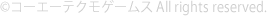- 2018.08.27
- 8周年記念シーズン「群雄繚乱」開幕!「8大特別企画」も!
 2018/8/26(日)で『100万人の信長の野望』は8周年!
2018/8/26(日)で『100万人の信長の野望』は8周年!8周年記念シーズンをはじめとする「8大特別企画」を開催!

 8/27(月)より8周年記念シーズン「群雄繚乱(ぐんゆうりょうらん)」が開幕!
8/27(月)より8周年記念シーズン「群雄繚乱(ぐんゆうりょうらん)」が開幕!ユーザー投票の上位20大名家が登場する
 オールスターシーズン
オールスターシーズン だ!
だ!真田幸村、織田信長、明智光秀など名だたる武将が率いる大名家に仕官可能!
天下に覇を唱えるのは一体どの大名家か!?
 「毎日35連ガチャ無料」キャンペーン開催!
「毎日35連ガチャ無料」キャンペーン開催!
「信長の野望」シリーズ35周年&『100万人の信長の野望』8周年を記念して、
 9/6(木)13:59まで毎日1回、35連ガチャが無料で引ける超豪華キャンペーンを実施!
9/6(木)13:59まで毎日1回、35連ガチャが無料で引ける超豪華キャンペーンを実施!
さらに、ユーザー投票で上位8位に入った大名家のランク11武将も登場!
 「ランク11極(きわみ)」新登場&ランク11武将が飛龍覚醒可能に!
「ランク11極(きわみ)」新登場&ランク11武将が飛龍覚醒可能に!
ランク12武将に加えて、ランク11武将も
ランク11武将をさらにパワーアップさせよう

また、今シーズンから
 「ランク11極」が新登場!
「ランク11極」が新登場!「ランク11極」は入手した時点で究極覚醒した状態になっているぞ。
この他にも、豪華キャンペーンが盛りだくさん!
詳細はゲーム内でチェックしよう
詳細はゲーム内でチェックしよう

 初期地図(大名家の配置)はこちら
初期地図(大名家の配置)はこちら

 ユーザー投票上位の20大名家に仕官可能!!
ユーザー投票上位の20大名家に仕官可能!!
本シーズンにて仕官可能となる20大名家を紹介!
仕える大名を見定め、
 天下統一を目指せ!
天下統一を目指せ!

|
 織田家 織田信長 織田家 織田信長天下布武(武力により天下を統一する)印の通り、戦国の覇者となる。明智光秀による本能寺の変により、炎の中に消えた。 |

|
 直江家 直江兼続 直江家 直江兼続上杉家の筆頭家老ながら、豊臣秀吉に評価され、大名並みに厚遇された。義や温情に厚く、戦では「愛」の字を前立てとした兜を用いた。 |

|
 伊達家 伊達政宗 伊達家 伊達政宗幼いころ病で右目を失い、独眼竜とよばれた。片倉小十郎、伊達成実らと共に東北に勢力を広げ、天下への野望を燃やし続けた。 |

|
 二階堂家 二階堂盛義 二階堂家 二階堂盛義須賀川二階堂家の当主。妻は伊達政宗の伯母・阿南。子・盛隆が蘆名家を継いだのを機に勢力を広げ、二階堂家の威勢を大いに回復した。 |

|
 北条家 北条氏康 北条家 北条氏康早雲に始まる後北条家の三代当主。関東全域に勢力を広げた。内政に優れたほか、日本三大夜戦の河越夜戦に勝利するなど、知勇を備えた将。 |

|
 井伊家 井伊直虎 井伊家 井伊直虎遠江井伊谷の領主。不幸が続いて跡継ぎがいなくなった井伊家を切り盛りする一方で、かつての婚約者の遺児である井伊直政を育て上げた「女城主」。 |

|
 上杉家 上杉謙信 上杉家 上杉謙信越後の龍。毘沙門天の化身を称し、「毘」の軍旗を翻して疾駆する姿は軍神と恐れられた。領土拡大ではなく義のために戦ったという。 |

|
 武田家 武田信玄 武田家 武田信玄風林火山の旗印で知られる甲斐の虎。武田二十四将と騎馬軍団を率い、天下を目指した。上杉謙信との川中島の戦いは特に有名。 |

|
 徳川家 徳川家康 徳川家 徳川家康江戸幕府の創始者。桶狭間の合戦後に自立し、豊臣家への従属を経て勢力を拡大。関ヶ原合戦で勝利を収め征夷大将軍となった。 |

|
 竹中家 竹中半兵衛 竹中家 竹中半兵衛卓抜した知略を羽柴秀吉に見込まれ、その軍師となる。天才軍師と称されるほどの軍略を駆使して多くの戦果を上げるも、36歳の若さで没した。 |

|
 前田家 前田利家 前田家 前田利家加賀百万石の祖。信長の小姓から手柄を重ね、愛妻まつにも支えられ、秀吉政権下では五大老に。甥の慶次は有名な傾奇者。 |

|
 大谷家 大谷吉継 大谷家 大谷吉継義に厚く、豊臣秀吉も一目置いた名将。関ヶ原合戦では、親友・石田三成のために病をおして奮戦、藤堂高虎の軍を撃退する。 |

|
 柳生家 柳生宗矩 柳生家 柳生宗矩柳生新陰流の宗主。大和・柳生の豪族だったが、父・石舟斎より剣術にて家康に仕え、のちに江戸幕府の将軍指南役となった。 |

|
 真田家 真田幸村 真田家 真田幸村日の本一の兵と称された名将。関ヶ原敗戦後、紀州九度山に蟄居。大坂の陣では父・昌幸譲りの兵法を駆使、赤備えを率いて活躍。 |

|
 豊臣家 豊臣秀吉 豊臣家 豊臣秀吉信長の草履取りから立身出世し、織田家の五大将に数えられるまでになる。姫路城を本拠に中国攻め中、本能寺の変が発生。明智光秀を討ち天下人に。 |

|
 毛利家 毛利元就 毛利家 毛利元就一豪族から始まり、中国地方を統一。息子の隆元、吉川元春、小早川隆景へ、兄弟の結束を三本の矢に例えたという話が伝わる。 |

|
 明智家 明智光秀 明智家 明智光秀美濃の名族に生まれたが、流浪の前半生の末、信長に仕える。筆頭家臣となるも、突如、本能寺の信長を討ち、一時は天下を握る。 |

|
 黒田家 黒田官兵衛 黒田家 黒田官兵衛号は如水。豊臣秀吉の参謀として、その天下統一に大きく貢献した。秀吉は、自身の死後に天下を取るのは官兵衛だと評価し、恐れていたという。 |

|
 立花家 立花ギン千代 立花家 立花ギン千代立花道雪の一人娘。道雪から男同然に育てられ、正式な手続きを踏んで立花山城督となる。のち高橋紹運の子・宗茂を婿に迎えた。 |

|
 島津家 島津義弘 島津家 島津義弘島津四兄弟の次男。島津家を隆盛に導いた家中随一の猛将。関ヶ原合戦では家康の本陣近くを敵中突破して「鬼島津」の名を高めた。 |